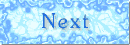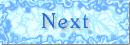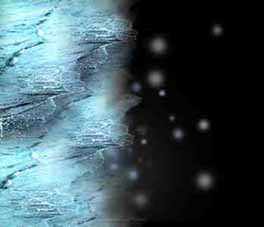
彼女の名は、北沢典子。神戸の貿易会社の社長の娘で、島の別荘に婆やさんと
一緒に来ているとの事でした。水泳が上手いのは、自宅の近くに浜寺水練と言って
当時日本で最も有名なスイミングクラブがあり、小さい頃からずっと泳いで居たそうです。
古くはベルリンオリンピック平泳ぎ金メダリストの前畑秀子を輩出し、
今でもシンクロナイズドスイミングのメッカになっているクラブです。
典子も中学生の時までは、水泳選手を目指して毎日練習に明け暮れていたのですが、
ある時心臓に欠陥が見つかって断念せざるを得なくなった、と言います。
であれば、あの時海に入っていったのは、自殺するような思いもあったに違い有りません。
「そんなこと、あらへんわよ。久し振りに泳いでみたかっただけよ」
と言って笑うばかりですが、お金持のお嬢様の割りに余り幸せそうでは無かったし、
性格的にも、なにかやけっぱちの激情といったものを感じさせる女〈ひと〉でした。
息を吹き返して、「なあんだ」と呟いたのも、すくなくとも死ぬ覚悟を決めて沈んで
行ったからでしょう。本人が思うほどあっけなく生き返った訳でもないのですが、
私は変な悪戯をした後ろめたさもあって、べつに苦労もしなかった、と言っておきました。
「泳ぐ事に掛けては、漁師の貴方より私の方が上手いわよ。
こんど一緒に競争しましょうか」
「いや、其れは認めますから、もう泳がん方がええですよ」
その夜私は、胸が苦しいと言う典子を背中におぶって、高台の別荘まで送届けたのでした。
そしてやっぱり、彼女の命の心配よりも、肩に触れる乳房の柔らかい弾力と、
掌にぴったりと貼り付いて来る様な太腿のなめらかな肌の感触とか、
そんな生々しい女体の気配に胸を塞がれそうに成って居ました。
別荘に着くと、直ぐ六十半ばぐらいの婆やさんが飛んで来て典子をベッドに寝かせ、
医者に電話をしました。
帰ろうとすると婆やさんは、私の手を取って拝まんばかりにして礼を言いました。
「海に浸かるだけや、て言うてはりましたけど、お嬢様は無茶しやはるお方やさかい、
わたしも心配してたんです」
婆やさんと医者には、一応事の顛末を正確に話さない訳には行かなかったのです。

それから一週間、典子はベッドに寝たきりで過ごしたようでした。
漸く心臓の状態も落ち着いて、その日婆やさんが私の家に来て、夕食に招待されました。
典子は、白いレースのドレスをきていました。おおきな楕円形のテーブルに二人きりで
向き合ってすわると、なんだか西洋のお城のお姫様と食事をしている気分でした。
最初に見た事も無いような高級ワインを出されたのにはチョツトたじろぎましたが、
食事はまとめてテーブルに並べられ、私の手元にはナイフとフォークやスプーン代わりに
割り箸も置いてありました。
田舎者に気を使って呉れたのでしょうが、私は以前に見よう見真似で覚えたぎごちない
手付きで、必死にナイフとフォークを使って食べて行きました。
典子はと言うと、まるでそんな作法などお構いなしに、
殆んどフォーク一本で食べていました。ステーキだって、
ねぇこれ包丁で切ってきてよ、なんて言ったりして、
しかしその食べ方は無造作な様でいて如何にも優雅でさまに成っていて、
なるほどこれがお金持のお嬢様の流儀かと感心させられました。
典子は、私よりひとつ上の二十一歳でした。前の年に神戸の短大を卒業して、
今は花嫁修業中だと、婆やさんが教えてくれました。
「船に乗って、夜の海に出てみたいな」と、典子が言いました。
答えかねて私は、婆やさんの方を見ました。婆やさんも、困ったような顔をしていました。
「ねぇ、いいでしょう?」
「そりゃぁ、まあ、かまわんけど」
「ああ、うれしい」
そう言って、ふわっと花が開いたように微笑み、それから婆やさんに向かって、
「あなたは、ついてきちゃだめよ」と何か釘を刺すような言い方をしました。
「さぁ、早くいこう」
典子は、一分でも惜しむように私のてを取って急かせ、別荘をでました。
白いドレスのままのすがたです。汚れますよ、と言っても、ええのよこんなもの、
と、まるで気にする風もありません。

花嫁衣裳のようでした。後年「瀬戸の花嫁」という流行歌が流行った時、
聞くたびに私は、あの時の典子の姿が目の中に浮かびました。
暫らく走った後、私達は豊島の西の沖の浅瀬に錨を下ろして船を浮かべ、
艫〈とも〉の甲板に並んで寝そべりながら円い月を仰いでいました。
「ねえ、抱いて。あなたが、好きよ」
典子のほうから、体を寄せてきました。普段は魚臭いだけの船なのに、その時、
私の鼻の周りには甘酸っぱい果実の匂いが一杯に漂っていました。
私ははにかみ微笑んでそのにくの薄い背中に腕を回していった時、急に胸の奥が
きりきりするような罪の意識が噴き上げてきて、思わず体を強張らせてしまいました。
夜の浜辺で仮死状態の典子に悪戯した事が、蘇ったからです。すきよ、と言われても、
もしあの事をしられたら好きだからこそ典子は余計に私を許せなく成るに違いない、
とそんな後ろめたさで頭の中が一杯になってしまったのです。
あの夜浜辺から別荘に帰る道すがら、私に背負われながら好きに成っていった、
と言うのです。その感情に、その時私が抱いていたような下品なスケベ心など
あるわけなく、もっと娘らしく純粋でロマンチックなものだったに違いないと思っていました。
しかし典子は、意外のことを呟きました。
「わたしの体は汚れてるの。そやから、遠慮なんかせんでもいいのよ。
あなたに一度だけでもの抱いて貰えたら、もう思い残す事はないわ。
わたし、親が勝手に決めた婚約者がいるの。その人、大嫌い。
私の事可哀相と思て、抱いてちょうだい」
やっぱり何やら、訳ありのようです。そんな切ない身の上話をされると、よけいに自分の
醜さが許せなくなります。
「生娘じゃない私なんか、嫌い?」
典子は私の顔を覗き込むように潤んだ瞳でそう言うのでした。